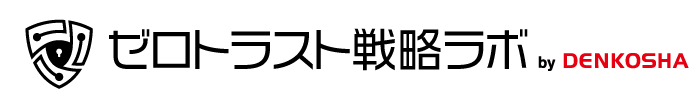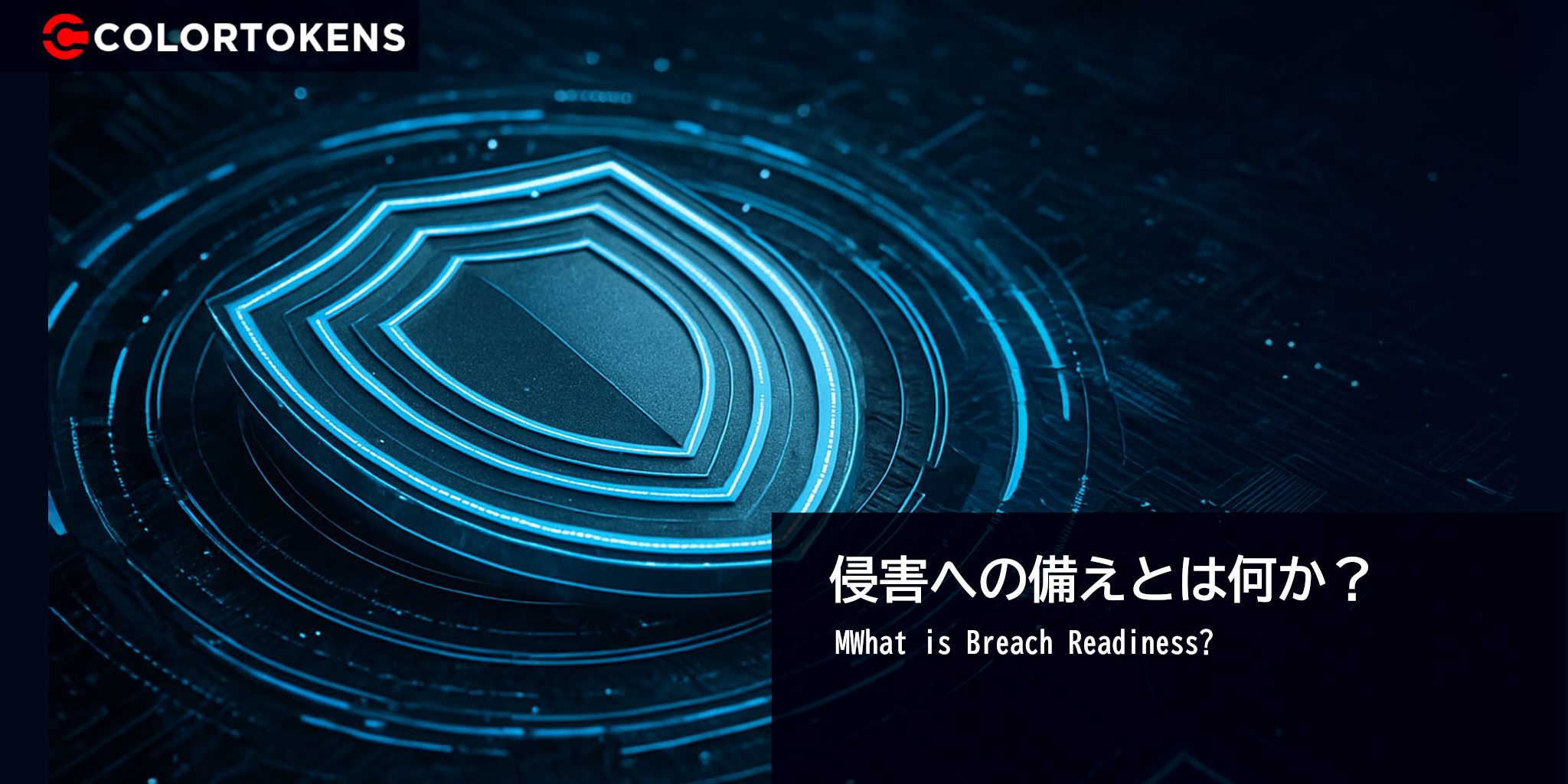侵害への備えとは何か?
多くの組織が境界での攻撃を阻止するために膨大なリソースを投入していますが、今日の脅威環境では異なる考え方が求められています。
侵害対応準備の概念は、インシデントが発生する可能性を認識することから始まり、その被害を抑え、軽減するための堅牢な方法を構築することを目的としています。
このアプローチには、技術だけでなく、侵害が発生した場合に運用を安定させるために必要なポリシーや計画も含まれます。
従来の多層防御を超える進化
従来、サイバーセキュリティの基本戦略とされてきた多層防御(Defense in Depth)は、複数の防御策を重ねることで不正アクセスを防ぐアプローチです。
重要な戦術ではありますが、攻撃者を防ぐことだけに注力するのでは不十分です。
真の準備は、攻撃者がこれらの防御策を突破した場合に何が起こるかを考えることに焦点を当てています。
この視点では、環境への可視性を維持し、迅速に脅威を封じ込め、侵害が重要なシステムに与える影響を最小限に抑えることが重視されます。
危機的状況への備え
真の侵害対応準備の重要な要素は、しっかりとした危機管理計画です。
このフレームワークには、侵害エリアを迅速に隔離し、脅威が広がるのを防ぐ能力が含まれます。
多くの場合、迅速な切断やセグメンテーションが、インシデントを封じ込めるか広範な問題に発展させるかの分かれ道となります。
効果的な危機管理は、異常が発生した瞬間に活用できる手順のツールキットと密接に結びついています。
事業継続性の強化
危機管理と並行して、現代の組織は、攻撃によってインフラの一部が中断された場合でも、重要な業務を維持することに焦点を当てる必要があります。
最小限の回復レベルが許容された時代は終わりを告げ、ビジネスは中断にもかかわらず機能の大部分を維持することを目指しています。
ここで、徹底的な業務影響分析(BIA)が非常に重要となります。
これにより、リーダーは、どのプロセスを確実に運用可能な状態に保つ必要があるのか、そしてそのために必要なリソースを特定することができます。
中核戦略としてのマイクロセグメンテーション
侵害管理のために議論されるさまざまな戦略の中で、マイクロセグメンテーションは特に革新的な手法として注目されています。
ネットワークを小さく隔離されたセグメントに分割することで、攻撃者が侵入後に自由に移動することが極めて困難になります。
この方法は、デジタル環境内にバリアを構築し、横方向への移動を最小限に抑えます。 ゼロトラストアプローチと組み合わせることで、各インタラクションにおいて継続的な検証が求められるため、単一の侵害が組織全体を危険にさらすことを防ぎます
Agnidipta Sarkar氏(ColorTokensのCISO Advisor)とDr. Chase Cunningham氏は、Dr. Zero Trust Podcastにおいて、侵害対応準備の概念と、それを達成する上で重要な役割を果たすマイクロセグメンテーションについて議論しています。
フルエピソードはこちらでご視聴いただけます:Being Breach Ready with ColorTokens
実装のための実践的なステップ
マイクロセグメンテーションを実行に移すには、慎重で計画的なプロセスが求められます。
まず、すべての資産、アプリケーション、データフローを詳細にマッピングし、セグメンテーションルールを適用すべき場所を正確に特定します。
ツールの導入に飛びつきたくなる誘惑を避け、徹底的な計画を立てることで、悪意のある攻撃者に利用される可能性のある設定ミスやギャップを防ぎます。
計画が完成したら、段階的にセグメンテーションを展開し、各段階で業務プロセスが維持され、安全であることを確認します。
経営陣の言葉で語る
サイバーセキュリティにおける最大の障害の一つは、特に予算を管理する非技術系の関係者に、マイクロセグメンテーションの価値を認識してもらうことです。
技術的なリスクに焦点を当てるのではなく、ダウンタイムがどれだけ回避できるか、顧客の信頼がどのように守られるか、長期的な混乱の財務的影響をどのように軽減できるかを強調します。
投資回収率を明確に示すことで、セキュリティ専門家はリーダーシップからより強力な支持を得ることができます。
現実の課題への取り組み
IT環境が進化を続ける中で、組織は急速に変化する技術、クラウドの拡大、リモートワークフォースに対応するのに苦労することがよくあります。
これらの状況は、最新のインベントリを維持し、セグメンテーション戦略を適応させることを困難にする可能性があります。
しかし、継続的なネットワークマッピング、定期的なポリシーレビュー、一貫したトレーニングを通じて積極的な姿勢を取ることで、インフラを強靭に保つことができます。
適切なツールを手元に置くことで展開の課題が軽減されますが、成功を確実にするのは初期の基礎作業です。
侵害への備えは技術だけではない
侵害対応準備を育むには、単なる技術以上のものが必要です。
攻撃の可能性を認識し、その影響を事前に制限するという先進的な考え方が求められます。強固な危機管理、堅牢な事業継続計画、組織全体の効果的なコミュニケーションを組み合わせることで、迅速な対応と回復の基盤が構築されます。
特にマイクロセグメンテーションは、攻撃者が足場を得た後の移動を著しく困難にする要となります。
今日の脅威環境で防御を強化することに本気で取り組むなら、その道は環境の詳細なモデリングと、トラブルが発生したときに迅速に行動する準備から始まります。
このアプローチの転換――攻撃を避けられないものと見なし、効果的に封じ込め、対応する戦略に焦点を当てること――が、強靭性を保つための決定的な違いを生むでしょう。
侵害対応準備を整え、業務を円滑に保つ方法についてご質問がある方は、ColorTokens(カラートークンズ)公式サイトからお問い合わせください。
翻訳元記事
「What is Breach Readiness?」
最終更新日:2025/1/25
著者:ColorTokens Editorial Team
※本記事では、アメリカのサイバーセキュリティ企業 ColorTokens(カラートークンズ)社が発信しているセキュリティ情報(英文)を、日本の代理店である株式会社電巧社が許諾を得て、日本語に翻訳して掲載しています
※記事は掲載後に修正される可能性がございますので、ご了承ください
※過去の記事もアップしておりますので、現在の情報と異なる可能性がございます。上記の最終更新日をご確認ください

この記事の著者:電巧社セキュリティブログ編集部