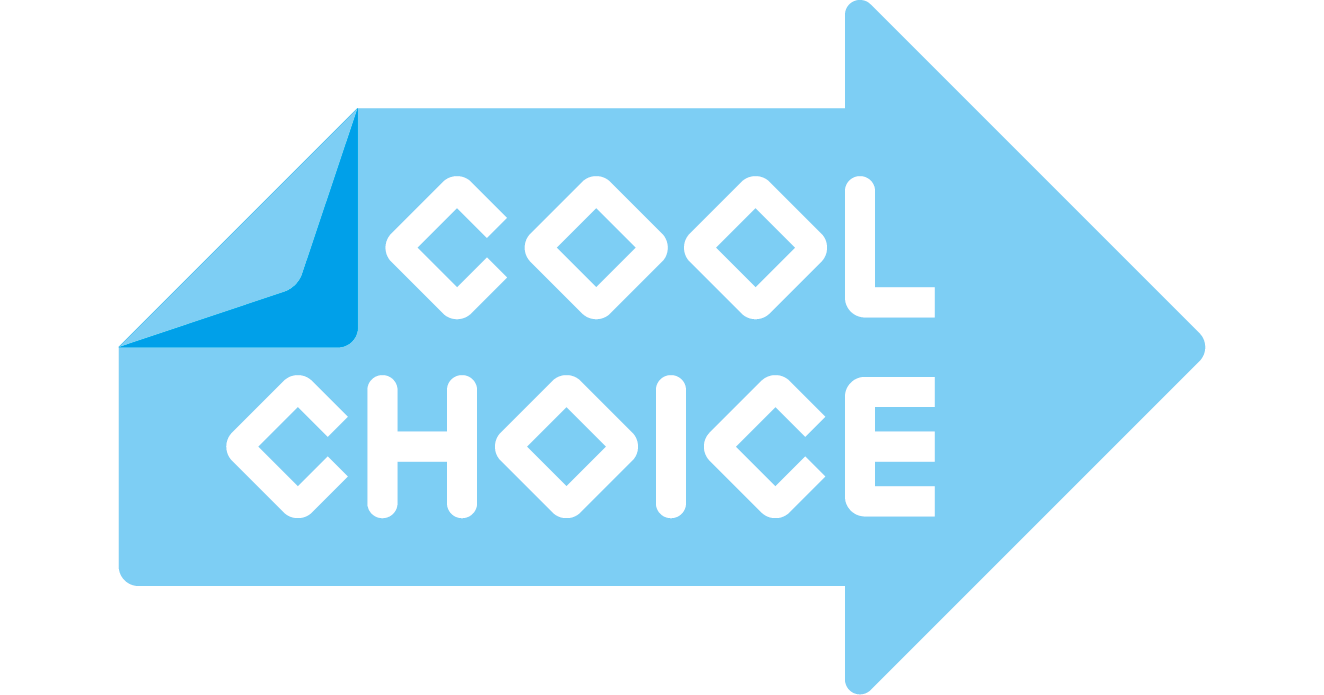DX実現に向け、社会のデジタル化が進みつつあります。
しかし、デジタル技術によって生活等の利便性が高まるに比例し、「デジタルリスク」も増加。
このリスクは現代社会に潜む脅威であり、企業の存続をも揺るがす危険性を秘めています。
デジタルリスクから自社を守るためには、どういった対策が必要になるのでしょうか。
デジタルリスクとは?
デジタルリスクは、デジタル技術やインターネット・SNSなどの利用に伴って引き起こされるリスクのことです。
このリスクは、企業がDXやデジタル化に取り組む中に多く潜んでいます。
アナログな業務では起こりえなかったトラブルや事故の原因となるため、然るべき対策が必要です。
会社の存続、そしてDX成功のためにもリスク発生を回避しなければなりません。
次に、デジタルリスクはどのような事故・被害を招く恐れがあるのか、詳しく紹介していきます。
デジタルリスクによる事故・被害の例
これから紹介する事故・被害は、全て実際に起こっているものです。
デジタルリスクに対し適切な対応を取っていないと、以下のようなトラブルが発生する可能性があるのです。

メールの宛先(TO)や、CCとBCCを間違えたことによる情報漏えい
メールの宛先(TO)を誤ってしまった場合は、記載内容や添付ファイルなどから情報漏えいにつながる危険性があります。
そして、CCとBCCの入力間違いは、メールアドレスの流出事故に直結します。
メールアドレスは、ドメインやアカウント名(ユーザー名)で個人を識別できるケースがあるため、個人情報として慎重に扱わなければなりません。
特に、CCとBCCの取り違えによるメールアドレスの流出事故は、頻繁に起こっている事故の一つです。
最近でも、このミスによる数百件ものメールアドレスの流出事故が、政府機関にて起こりました。
不適切な投稿をしたことによる企業イメージのダウン
SNSや動画投稿サイトへアップした内容に対し、一斉に批判・非難を浴びることを、炎上といいます。
過去には、アルバイトの悪ふざけによる投稿で、倒産にまで追い込まれた企業も存在します。
炎上は、イメージダウンと共に、企業ブランドにも深くキズをつけてしまいます。
インターネットに掲載した情報は、半永久的に残ってしまうことから、デジタルタトゥーと呼ばれています。
デジタルタトゥーによるネガティブイメージを完全に消し去ることは、ほぼ不可能といってよいでしょう。
サイバー攻撃(ハッキング等)の被害
不正アクセスによってWEBサイトの情報が改ざんされ、悪意のあるサイトへ誘導されるように書き換えられていたり、サイト登録者の個人情報が抜き取られたりといった事故が、近年頻繁に発生しています。
このように、不正な手段でシステムを操作されることをハッキングといいます。
被害の発生件数は年々伸びており、企業への被害も増加。
サイバー攻撃によって第三者へ被害が及べば、損害賠償責任を負わなければならない可能性もあるのです。
そうなってしまうと、企業の社会的信用も落ちてしまいます。
システム障害によって業務・サービスが停止
ニュースでよく目にするようになったシステム障害。
システム障害が原因で、サービス提供やWEBサイトが停止してしまい、何億円もの損害を被った企業は少なくありません。
システム障害が起こってしまうと、自社業務だけでなく顧客にも大きな影響を与えます。
そうすると、本来得られるはずだった利益、そして信頼を同時に失ってしまいます。
障害発生の原因は、主に外部要因と内部要因の2パターンがあり、人的なミスだけでなく、自然災害などの予期せぬ事態で起こることもあります。
迅速な対処・原因解明ができる体制を整えていないと、損害は拡大してしまうでしょう。
PCやUSBの紛失に伴う情報漏えい
つい最近、何十万件もの個人情報が入ったUSBの紛失事故が起こり、世間を騒がせました。
テレワークが普及し、場所を選ばずに働けるようになったことは、働き手にとって大きなメリットです。
しかしその一方で、PCやUSBを持ち運ぶことによる紛失・盗難リスクもぐんとアップしました。
万一の場合を考えて、パスワード設定や暗号化によって中のデータを保護していても、不正アクセスまたはシステムの破壊・改竄が行われると、データが盗まれる恐れも。
その他にも、手放したHDDからデータを復元され情報が流出したり、ダウンロードソフトからウイルス感染してしまったりと、デジタル関連の事故・被害は数え切れないほど発生しています。
これらはどの企業にも起こる可能性があり、決して他人事ではないのです。
リスクを未然に防ぐには
企業のデジタルリスクを未然に防ぐためには、以下の4つの対策が効果的です。
- 従業員のITリテラシー向上の取り組み
- 不正アクセスやウイルス感染を予防するためのセキュリティ強化
- 必要に応じてルールを設ける
- ツールやサービスはセキュリティ対策がしっかりしたものを選ぶ

ITリテラシー向上の取り組み
まずは会社全体でITリテラシーを高めていくことが重要です。
メール送信のミスやSNS炎上などのリスクは、従業員のITリテラシーを高め、ルール化することで未然に防ぐことが可能です。
企業は、従業員がデジタル技術を正しく利用できるようにするためにも、IT知識を学べる環境を設けるなどの措置が必要です。
デジタル化が進む現代社会にて、企業価値や情報資産を守っていくためにも、この取り組みは必要不可欠と言い切って良いでしょう。
今や、ITに携わる部門だけでなく、誰もがネットワークやセキュリティの基礎知識を持つべき時代なのです。
不正アクセスやウイルス感染を予防するためのセキュリティ強化
DXを推進していくにあたり、セキュリティ対策や強化は、必要不可欠な取り組みです。
情報資産を守るためにも、第三者からの悪意を跳ね返す堅牢なセキュリティを構築しておかなければなりません。
セキュリティ対策を経営課題と捉え、取り組めることができれば、自社だけでなく、従業員や顧客を守ることにつながります。
また、脆弱なパスワードを設定しないなどの、初歩的な対策も忘れてはいけません。
推測しやすいパスワードは、不正アクセスやサイバー攻撃の的になります。
こういった最低限の取り組みも、従業員にも繰り返し周知し、万が一に備えておきましょう。
必要に応じてルールを設ける
ソーシャルメディアガイドラインという言葉をご存じでしょうか。
社内にて、SNSなどのソーシャルメディアを利用する際の方針を打ち出したものを「ソーシャルメディアガイドライン」と呼びます。
昨今では、デジタルリスク対策としてこのガイドラインを策定し、公表している企業も増えています。
このようにルールを設けることで、不確かな情報の発信や、不適切な内容の投稿を防ぐことができるのです。
また、重要なメールの送信やSNSへの投稿を行なう前に、社内でダブルチェックを行なうこともリスク回避につながります。
ツールやサービスはセキュリティ対策がしっかりしたものを選ぶ
導入するITツール・ソリューションは、セキュリティ対策がしっかりしているものを選びましょう
たとえば、電巧社のAI-OCRソリューション『AI-Smart Reader』は、
通信部分・クラウド内での通信部分・データベース の3か所で暗号化処理を行っており、セキュリティ性を高めています。
また、データ保管時に、順不同かつ連続性が想定できない形へと処理する仕組みとなっており、万が一の時でも個人を特定できないようになっています。
このように、ITツールやソリューション、サードパーティ製品などを選ぶ際には、サービスの安全性をチェックすることが大切です。
サイバーセキュリティが気になる方は、ぜひこちらのページをご覧ください。
AI-Smart Readerが気になる方は、ぜひこちらのページをご覧ください。
まとめ
DXが進めば進むほど、企業は多くのデジタルリスクに晒されます。
故意はなくとも、ちょっとしたミス、知識不足が企業を脅かすリスクになり得るのです。
事故やトラブル発生の可能性を最小限に抑えられるよう、対策を練っておきましょう。
自社のセキュリティ対策がおろそかになっていないか、今一度チェックしてみてください。
商品に関するご相談・お問合せはこちら
オンライン相談実施中!
弊社より無理な売り込みはいたしません。
お気軽にご連絡ください。
おすすめ記事