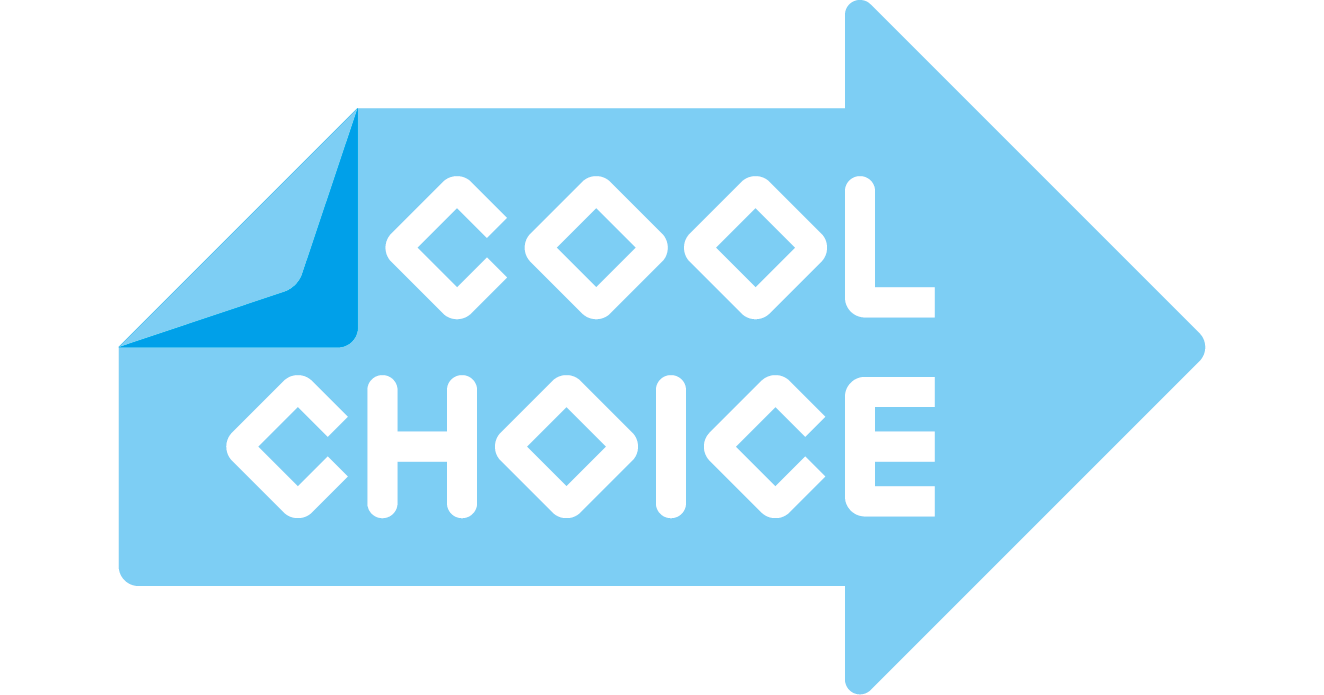帳票に記載されている日付を知りたい、あの書類にサインした社員は誰だっけ…。
業務遂行において、書類の内容を確認しなければならないことってありますよね。
しかし、必要な時に限って書類が見つからない!そんな経験はありませんか?
今回は、書類保管に役立つ情報をご紹介します。
書類整理が苦手な方や、効率良く書類保管したいという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
書類保管の重要性とは
社内で取り扱う書類にはさまざまな種類があります。
業務報告書や契約書、請求書、計画書など…例を挙げるときりがありません。
こういった書類は機密情報が記載されているものが多く、きちんと保管・管理することが企業の務めです。
また、法律で保管が義務付けられている書類もあります。
万が一書類を紛失してしまうと、情報漏えいにつながる恐れがあります。
情報漏えいの発生事故は、社会的信用に影響を与えるため、企業にとって非常に大きな損失に。
場合によっては、損害賠償責任も負担しなければならず、流出した情報の数や二次被害の規模によって賠償金を支払う義務が発生します。
必要な時に見つけやすくするだけでなく、こういったリスクを避けるためにも、書類は適切な方法で保管しなければならないのです。
まずは書類を分類しよう
書類保管は、種類ごとに分類するところから始める必要があります。
本記事では、一般的に有名な3種類の分類方法を紹介いたします。
ぜひ、自社にはどの方法が適しているか、考えながらチェックしてみてくださいね。
部署間で情報共有がしやすい【 割り付け式 】の分類
この分類方法は「会社全体で分類ルールを決めておく」ことが特徴です。
まずはざっくり大きく分類した後、中分類、小分類…とトップダウン型で仕分けていきます
割り付け式は、全部署同じルールで書類が仕分けられるため、部署間で情報共有しやすくなることが大きなメリット。
その反面、部署特有の細かい書類まで考慮したルール作りが難しいことが懸念されます。
柔軟に仕分けることのできる【 積み上げ式 】の分類
こちらは「実際に書類を取り扱う担当者が保管書類ごとに分ける」方法です。
割り付け式とは反対に、小分類から仕分けをスタートし、中分類、大分類と分けていきます。
実際に業務に携わる社員が分類ルールを決めていくため、新しい書類が出てきたとしても柔軟な対応が可能です。
デメリットとして、全社で情報共有がしにくい点や、他部署の人が書類を探しづらいという点が挙げられます。
割り付け式×積み上げ式【 ハイブリッド式 】の分類
割り付け式・積み上げ式のよいとこ取りの分類方法です。
「ある段階までしっかりルールの定まった割り付け式で分類した後、細かい部分は積み上げ式で分類」していきます。
人によって保管の方法がバラバラになる恐れがあるため、割り付け式部分のルールはしっかりと決めておきましょう。
どの方法にもメリットやデメリットは存在するため、それぞれを比較しながら分類方法を決めるのが良いでしょう。
また、書類の分類時は「保管期間が決められているか」「紙での保管が必要か」「すでに破棄してよいものか」なども確認しておく必要があります。
法律や業界のルール、会社で決められている保存期間や保管方法を遵守しましょう。
ファイリングの方法
書類を分類し終わった後はファイリングし、キャビネット等へ保管していきます。

ファイルは同じ種類のもので統一するのがベター
書類を入れるファイルは、なるべく同じものを揃える方が良いでしょう。
異なるサイズのファイルで保管を進めると、キャビネット内にデッドスペースが生まれてしまいます。
背表紙に書かれた文字の高さにもバラつきが生まれ、視認性も悪くなります。
色や番号で種類分けするのも◎ 保管順にも配慮を
さらに見やすくしたい場合は、書類の種類ごとにファイルの色を変えたり、番号を振ったりすることをおすすめします。
ラベルのフォントを揃え、貼る場所を統一するだけでも、“探しやすさ”はアップします。
また、キャビネットへの保管時は、ただ並べるだけでなく、順番を考えて格納していきましょう。
閲覧頻度の高いものが一番取り出しやすい位置にくるようにしたり、発行日や50音順に並べたりと一工夫すれば、より書類を取り出しやすくなります。
データで保管場所を管理するとさらに便利
さらに書類を見つけやすくしたい方は、書類ごとに分類番号を付け、“書類管理表”としてExcelなどにまとめておくとよいでしょう。
「Aファイルの23番目に格納してある申込書」であれば、「申込書:A-23」といったように、書類の種類・ファイル名・ファイル内に格納されている場所(順番)を記録しておきます。
まとめる表には申込書名や企業名、日付などの情報と保管場所を記録すると、書類のデータベースのような形に。
ちょっとした情報を知りたいときにとても便利です。

▲書類管理表の例(Excelで作成)
ただしこの方法は、書類探しの時間短縮ができる反面、表に情報を入力するという手間が発生します。
できれば、入力の手間を省いたうえで、書類を探す手間を短くしたい…。
そんな方には、文字をデータ化するソリューションの活用がおすすめです。
「文字をデータ化」するソリューションで効率的な書類管理を
文字認識の精度が高いAI-OCRソリューション【 AI-Smart Reader 】
電巧社では『AI-Smart Reader』というAI-OCRソリューションを提供しております。
AI-Smart Readerは、紙に記載された手書き文字・活字をテキストデータ化してくれる商品です。
使い方は簡単、複合機などでスキャンした書類データをアップロードするだけ。
初回のみ、読み取る書類や帳票の定義が必要ですが、2回目以降は不要です。
その名の通りAIが搭載されており、文字認識率が非常に高いことが特長。
読み取ったデータは、CSV形式でダウンロードできるので、報告書の作成や集計作業などに活用できます。
原本はファイリング、スキャンデータはPCに保管。
そしてAI-Smart Readerでデータ化した情報は、業務での活用+書類管理表へと反映。
そうすれば、書類を探すために費やしていた時間を大幅に削減できるでしょう。
AI-Smart Readerが気になる方は、ぜひこちらのページをご覧ください。
紙帳票デジタル化クラウドサービス「onboard Tablet Lazuli」
まるで紙に書いているような書き心地の専用ボードソフトウェアキーボード操作がほぼなく、リアルタイムテキスト変換、既存の帳票を使ってデジタル化が簡単に出来るクラウドサービスです。
onboardの詳細は、こちらのページをご覧ください。
このように、ファイリング保管とあわせて、データ化した書類を保管できれば、必要なときにすぐ内容を確認できるようになります。
また、書類内容の入力・転記作業も自動化するため、業務効率が大幅にアップします。
まとめ
会社から紙書類を“完全に”なくすことは簡単ではありません。
だからこそ、紙もデータも分かりやすい方法で保管しておくことが大切です。
自社に適した分類・ファイリング保管を行い、必要な書類を必要な時にすぐ手に入れられる環境を整えておきましょう。
いかに、探す時間を短くするか。
毎日15分かかっている書類探しを5分にできれば、なんと月200分もの時間を生み出せます。
「業務効率化」のために、ソリューションを活用した書類保管・管理を検討してみてください。

取扱商品一覧
電巧社では、DX推進に役立つサービスをはじめとして、ビル用電気設備や産業用機器、再生可能エネルギーに関連したサービスを展開しています。
おすすめ記事